かつて桂冠詩人になると人が死ぬ、あるいは、別の言い方をすれば、英国の公式な国民詩人は伝統的にハーネスで死んでいたのです。 アンドリュー・モーションが 1999 年から 2009 年の 10 年間在任するまでは、「次はどうするのか」という質問に答える余裕などありませんでしたが、この間、この役割の改革により、その任期がわずか 10 年に短縮されました。 この時点でコンサルティング会社の言葉を引用するのは奇妙に思えるかもしれませんが、高給取りの仕事をしていたクライアントが新しい社会人生活を築けるよう支援するアイリードは、瞬間的なキャリア「ハイ」の後に次に進みたいと考える人々に対して、4つの戦略を用意しています。 823>
女性初の桂冠詩人であるキャロル・アン・ダフィーは、現在この4つのすべてに取り組んでいる。 COVID-19のパンデミックの間、彼女は2019年5月に退任してから初めてマスコミに本格的に登場し、彼女が常に行ってきたこと、すなわち慰めと善の力の源として大衆に詩を提供したことは、それを物語っている。
ダフィーはまた、新しい共同詩のプロジェクトを立ち上げ、暗闇の中にさえ創造性を見出すことで、苦しみに正面から立ち向かうという特徴的な行動をとっている。 823>
Business as usual
私の仕事は、桂冠詩人の役割は、あなたが作るものであることを他の場所で示してきました。 いつ詩を書くべきか、何について書くべきかをマスコミや大衆が決定する権利を与えられているような「公有」の役割であるため、大変な仕事に思えるかもしれません。 たとえば、2011年のロイヤルウェディングでのダフィーの沈黙は、しばしば批判の的になっている。
しかしダフィーは、まったく正しく、自分が言うべきことがあると感じたときだけ書くという決意を見せている–だから彼女は、2018年のハリー王子とメーガン・マークルの結婚に際して詩『Long Walk』を書いたのである。
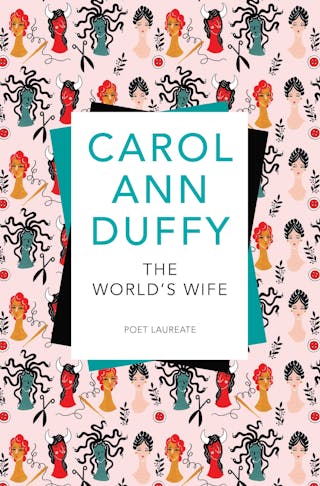
一般論として、受賞の名声は彼女を変えていないように見える–彼女は相変わらず激しく私的で、公の場では自制し、有名人よりもむしろ詩の未来に焦点を当てているのである。
ダフィーは、他の元受賞者よりも「次はどうするのか」という問いに答えるのに適した立場にいる。なぜなら、彼女は20年以上にわたって、作品の中で再出発というテーマについて考察してきたからだ。 受賞が始まる10年前、彼女は最も有名な作品集『The World’s Wife』(1999年)の最後に、詩『Demeter』を発表している。 ペルセポネは半年間冥界に縛られるが、残りは母デメテルと過ごすことを許されるというギリシャ神話を、フェミニストに再構築したものであった。 ダフィーの詩は、「新月の小さな恥ずかしそうな口」を歓迎することでこの詩集を終えているが、この文脈では、母と娘の間の再出発の象徴を表している
その後の詩も、新しい出発について考察している。 ダフィーの桂冠詩人としての最初の作品集『The Bees』(2011年)の中の「Snow」では、死者が生者を動けなくし、文字通り散らばった一握りの氷で彼らの行く手を阻み、元桂冠詩人なら誰もが自問し、この大流行の中で私たちを鼓舞するかもしれない問題を提起しているのである。
Cold, inconvenienced, late, what will you do now
with the gift of your left life?
Starting over
再び始めることには、何か深い魅力があります。しかしダフィーは、これは古い生き方の喪失を悲しむ文脈でしかできない、たとえば2005年の《携》では、エロティックな絆の破壊を嘆く、と示唆しています。 一方、2018年に出版された『真心』は、桂冠詩人としての最後のコレクションとなったが、子どもの家出によって家族単位にもたらされた変化を嘆いている
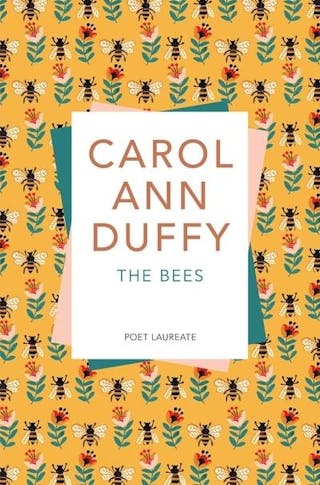
しかし、やり直すことは、共同体の政治的行為でもあることを、ダフィーは思い起こさせる。 これに対する彼女の反応は、今のところ3つである。 第一に、彼女はトラブルを引き起こす。 A Formal Complaint (Sincerity)』のような詩は、個人の選択や声が持つ潜在的な力を思い起こさせる。 フェイクニュースとスピンに焦点を当てた資本主義の政治システムは、私たちが抵抗するにはあまりにも組織的な繕いの力に見えるかもしれません。しかしダフィーは、一度に一つの嘘を観察し、すべての半分の真実、すべての不当な社会政策を呼び出すために、私たちに静かに呼びかけるのです。
そうすることで、文化は誠実であり続けることができる(それゆえ、彼女の作品集のタイトルには「Sincerity」が使われている)。 これは、20世紀の作家であり哲学者であるジッドゥ・クリシュナムルティが有名な文章を書いたことと呼応しています。 “重病の社会にうまく適応することは、健康の尺度ではない”。
Reasons to be cheerful
Duffyもまた、絶望的なときでも幸せになることを許可し、ありえない場所で喜びをつかむことを勧めているのです。 モンキー(真心)」は、1970年代のシュールレアリズムの原点に立ち返った作品です。
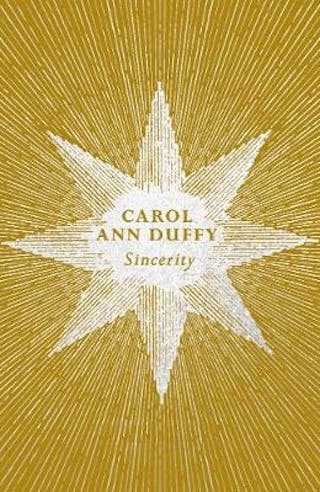
イタリアでの休暇中に衝動買いした霊長類は、彼女に母親としてのセカンドチャンスを与え、それがどんなに不思議であっても本当の喜びをもたらし、「可能性に」驚嘆しながら永遠に休暇をしっかり過ごすことを決意させる。
この詩の中で彼女が言及するヨーロッパの太陽、戻ってきた愛、笑い、健康な生活、毎晩のバナナダイキリは、この詩の教授職と月桂冠の言及によって象徴される過労のイギリス文化的安置よりも、「引退」への期待、言葉、詩そのものと遊ぶという行為自体がはるかに意味をなしています。
ダフィーは、私たち自身の世界の重さにはりつけられたと感じる人々が見習うべき、堂々とした態度でこの詩を終えています:
As for my University Professorship, I shall resign. 猿は私のものです。
。