ローリング・ストーンズは、1960年代に英国で結成されてから50年以上たった今でもツアーを続けています。
バンドに関する本は何棚もありますが、新しい本「The Cambridge Companion to the Rolling Stones」は、彼らの音楽とその遺産を学術的に考察しています。
この新しい本の編集者の一人で、ボストン大学の音楽教授でもあるビクター・コエルホは、この本は音楽史におけるストーンズの役割を広く見ている、と述べています。
「ストーンズの自伝は、深い音楽的知識、デルタ地帯やカントリー・ミュージック、アメリカの風俗習慣に至る長い影響、さらには映画での存在感やその大きな文化的影響を、直接教えてくれるものがたくさんあります」と彼は述べています。 「
コエーリョは、ローリング・ストーンズがその長いキャリアの中で、ロックンロールとブルースのルーツに忠実でありながら、新しい音楽トレンドに適応し、先取りすることができたと述べている。
「この本は常に、ストーンズがどのようにスタイルに適応し、適応しても、根本的に影響を受けたものに忠実であることを理解できる方法として位置づけられていた」と、彼は言う。 そして、そのすべてが、彼らの最後のアルバムである『Blue & Lonesome』では、本当にブルース時代に戻ったような曲の数々となっています」

Interview Highlights
1968年から1972年までのローリング・ストーンズのサウンドについて
「私はその時期を亡国時代と呼びましたが、文化史上非常に有名な亡命者、たとえばダンテやソルジェニツィンや悪魔であれ、最初の亡国者のように、ほとんど自らに課す亡国者とする年です」
「私は、そのような年であったと思います。 イギリスから目を背けているのです。 つまり、彼らの最初の時期、私はいつもこの3つの時期をイギリス、特にロンドンと見ています。そしてアメリカは1968年に大きく開国しました。 そして最後の時期が、1989年以降のリバイバルで、私はこれを「第二の人生」と呼んでいるのですが、彼らは自分たちの歴史をほとんど演奏博物館としてキュレーションしているのです」
「しかしこの時期は、彼らがアメリカに向かって、アメリカの深い音楽の伝統に向かって向き始めた時期なのです。 彼らは、貴族階級のイギリスとの対決や、「サティスファクション」や「ルビー・チューズデー」、その時代のさまざまな歌にまつわる階級的な挑戦を置き去りにしてきたのです。 そして今度はアメリカへと向かい、グラム・パーソンズやライ・クーダーなどアメリカの偉大なミュージシャンの影響を受けて、アメリカの風土に根ざしたスタイルへと深く深く入り込んでいくのです。 そして、彼らは方言を拾い始め、その方言はミシシッピやカリフォルニアのベーカーズフィールドの方言であり、カントリー&ウエスタンや新しいギタースタイルである。 そして、これらの方言は彼らの音楽に浸透し始める。 それが彼らの音楽を古くもなく新しくもないものにしている。 1388>
「ギミー・シェルター」という曲の意義について
「聴くたびに、何か違うものが聴こえるんだ。 しかし、私が聞く1つの基本的なものがあり、それはこのアルバムの冒頭で、かなり暗いものです。 その暗さは、まさに1969年、ムーンショットと同じ年なのです。 ウッドストックと同じ年でもある。 アルタモントでのストーンズのコンサートでは、ヘルズ・エンジェルに刺されてコンサート参加者の一人が死亡しています。 この曲は、バックグラウンドでのハウリング、短調のオープニング、曲全体を通して続く下降進行など、驚くほどこのことを予期しています。 そしてクライマックスの「レイプ、殺人」という言葉。 一発で終わるんだ」という言葉がクライマックスになる。 つまりストーンズは、この曲を69年を物語るものとして設定したわけです。 そして1969年は、本当にウッドストックのことではないんだ。 まだベトナムのことなんだ。 ストリートでの暴力についてもそうだ。 プロテストについてもそうだ。 そして、アメリカの大部分を包んでいる暗闇のことでもある。 ウッドストックは後世の記憶だ。 1388>
ストーンズについてどのように多くを学び、彼らが音楽について何を教えたかについて
「私はプレイヤーであり音楽学者なので、私にとってストーンズが誰と付き合っているか、どんなクラブに行っているか、そういったことにはそれほど興味がありませんでした。 私はいつも音楽に興味があり、それが第一だったのです。 ローリング・ストーンズのクラスでは、私はギターの後ろから教えます。 常に音楽について、そして影響についてです」
「ストーンズは私にとって、他のスタイルに導いてくれる場所でした。 彼らは私を導いてくれたのです。 中略)私は彼らのようにシカゴのブルース・リバイバルにたどり着いたわけではありません。 私は彼らのようにシカゴ・ブルース・リバイバルに辿り着かなかった。 だから、ロバート・ジョンソンに導いてくれたのも彼らだし、カントリーミュージックに導いてくれたのも彼らだ。 だから、マール・ハガードを聴くようになったのも、彼らを通じてだったんだ。 ナッシュヴィルやさまざまなチューニングについて考えるようになったのも、彼らからでした。 彼らは私を様々なスタイルに導いてくれました。 フランスのニューウェーブ映画にも導いてくれた。 ブルガーコフの「マルガリータ」を読むように導いてくれたのも彼らです。 だから、他のグループにも導いてくれたし、レゲエにも導いてくれた。 1388>
今日のローリング・ストーンズのパフォーマンスを見るのはどんな感じか
「つまり、彼らはまだあの音を持っているから、いつも同じなんだ。 そしてまた、ストーンズの音、それが最も重要なことなのです。 彼らは偉大なブルースマンのように見えるんだ、それが彼らの姿であり、そうあるべき姿なんだ。 ロックというのは面白いジャンル、スタイルで、若者の娯楽ということを完全に超えてしまっているからね。 ロックは音楽史の1つのスタイルなのです。 そして私はストーンズの年齢を、ちょうど75歳の指揮者を見るように見ています」
ローリング・ストーンズのお気に入りの曲について
「いつも変わりますが、今は『ベガーズ・バンケット』からの『ストリートファイティングマン』をよく聞くようになりましたね。 そしてまた、その録音の音に何か感じるものがあるんだ。 というのも、私たちは皆、ヘッドフォンで音楽を聴いているので、音とは何かというダイナミズムを失ってしまっているのです。 MP3形式で圧縮された音楽を聴いている。 ストーンズの音楽は、レコードから飛び出してくるんですよ。 レコードに針を刺すと、ヘッドフォンでは再現できないような音が出てくるんだ。 ストリート・ファイティング・マン』もそのひとつだ。 ギターの音がね。 スタジオでは、キースがあのリフを弾いているテープレコーダーにマイクを置いたから、第3世代みたいなフォーマットで出てくるんだ。 これほど素晴らしいものはない。 それが今でも印象に残っているんだ。 1388>
アレックス・アシュロックはキャサリン・マッケンナとの放送のためにこのインタビューを制作・編集した。 Samantha Raphelsonがウェブ用に脚色した。
Book Excerpt: 7702>
By Victor Coelho
Exile, America, and the Theater of the Rolling Stones, 1968-1972
Lucifer と Prodigal Son についての聖書の一節から乞食、罪人、不審者、中毒者、放浪者、黒人過激派、グルービー、道に疲れたトラブルツアーについての物語まで幅広い歌詞があります。 音楽的影響の網は、都会と田舎のブルース、カントリー、カリプソ、R&B、ロックンロール、フォーク、ゴスペル、そしてイギリスの合唱の伝統まで、色とりどりの糸で紡がれているのである。 1968年から1972年にかけてローリング・ストーンズがリリースした4枚のアルバム、Beggars Banquet、Let It Bleed、Sticky Fingers、Exile on Main Streetは、評論家、ファン、歴史家にとってグループのコア・アイデンティティであり、ストーンズの音楽、歴史、文化の遺産を形成した永続的で標準的なレパートリーであったと言える。 ジャック・ハミルトンがストーンズの最近の研究で書いているように、1968年からエグザイルまでのバンドの年月は、”すべてのポピュラー音楽において、持続的で偉大な創造のピークの一つ “に相当する。 ローリング・ストーンズが音楽史の中で特別な位置を占めることが保証された瞬間について、ローリング・ストーンの創始者ジャン・ウェナーは内部からの視点を提供している。 1970 年にグループがアレン・クラインと ABKCO のマネジメントから抜け出したとき、ウェナーはワーナー・ブラザーズのモ・オスティンに、遅滞なくグループと契約するよう懇願した。 彼らは更新していません。 彼らはアメリカで新しいレーベルと会社を探していますが、自分たちのレーベルではありません。 彼らは現在2枚のLPをリリースする準備が整っています。 Live in the USAと、Muscle Shoalsから完成させた、あるいは完成させたLPです。
Mick Jaggerが彼らの新しいレーベルを決定します。 この契約を得るためには、損をしてでも手に入れる価値のあるものだ。 ストーンズを獲得したレーベルは70年代の勝者のひとつになるだろう。
ロンドンのミックに直接コンタクトを取るなら、MAY 5856, 46A Maddox Street, W1. NOW.
半世紀前のリリース以来、出版物やビデオで幅広く記録されてきたこれらのアルバムに対する批評家の評価は、1960年代後半から1970年代初頭の政治的、世代的緊張の中で、その歴史的関連性をより強固なものにしてきた。 特にLet It Bleedの「Gimme Shelter」(曲と映像の両方)は、1969年7月のウッドストックの理想郷から、わずか5ヵ月後のアルタモントの悲劇という「ウッドストック国家への真珠湾攻撃」のようなディストピアの現実への突然の変化を伝えるライブ放送として不滅に語られている。 また、『ベガーズ・バンケット』に収録されている「悪魔への共感」は、ベトナム戦争とそれに関連する抗議運動と表裏一体となった1968年のアメリカにおける不安定な活動、暗殺、人種間の緊張を語る上で、どこでも参照できるポイントとなっている。
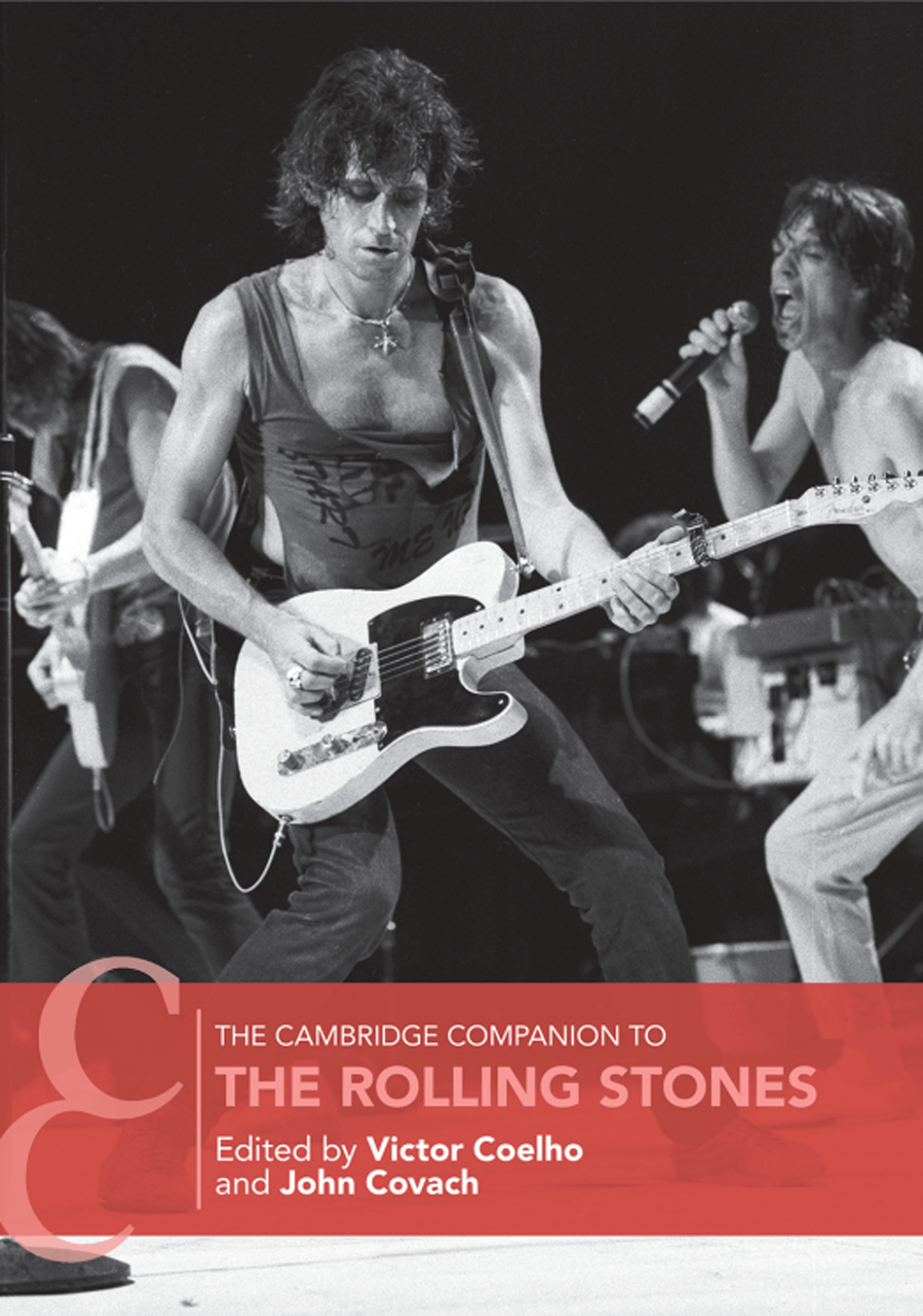
ゴダールの1968年の観察映画「One Plus One」は、ストリートで発生するマルクス主義のアナーキーの比喩として「悪魔への共感」がゆっくりと進化することに断固たる焦点を当て、非常に先見の明があり、その予感はジャガーも共有していた。 「パリの学生暴動に先立つ1968年5月、ロンドンのグロヴナー・スクエアでの反ベトナム抗議デモの最中、彼はインタビューで「循環的な変化があることは間違いない」と語っている。 私は、アメリカがただ燃え上がり、ただ破滅していくのを想像することができる……」。 最後に、『メインストリートの流刑地』は、スタイル的には新境地を開拓していないが、このアルバムの詩的で生きた地理的な流刑地というテーマを通じて、ストーンズの永久的なアイデンティティを後世のために枠付けしている。 前作までの音楽的多様性の集大成であり、彼らのスタイルの深いルーツが現在にむき出しになっている。 エグザイルの音楽的ボキャブラリーには、古いものも新しいものもない。 ジャノヴィッツがこのアルバムの研究で書いているように、「自らに課した制限を楽しんでいるようだ」。 実際、それは時に古めかしく聞こえる。 また、あるときは完全に現代的でモダンなサウンドに聞こえる。 1388>
この4枚はストーンズの最も売れたアルバムではないし、約400曲のカタログのうち57曲が、彼らのレコーディング史の5年間のどの期間においても非常に多くの楽曲が集中しているわけでもなく、1968年以前と1972年以降にははるかに多くの曲が録音されている。 しかし、1968年の『Beggars Banquet』から、ロックンロールの方言の深化が見られる。グループが、都会のブルース、モッズ・ロンドン、エド・サリバン・ショーの中産階級の聴衆といったメトロポールへの関心から、広いアメリカとその「遠い」伝統であるデルタブルース、田舎の田舎、古いテキストという新しい風景に旅している。 彼らはこれらのジャンルや歌詞のテーマに、革命的で破壊的、そして人種や世代間の争いに満ちた現代文化のメタファーとして、距離と真正性という生の亡命者としての特質を吹き込んだのである。 以前の亡命者と同じように、彼らは参加と再出発の岐路に立たされました。 このグループは社会の深い暴力と闘争を認識しながらも、批判的で詩的な距離で行動から切り離され、戦闘ではなく、解説を提供することにとどまっていました。 ジョン・ランドウが『ローリング・ストーン』誌に書いたように、
このアルバムで最も驚くべき曲は、ストーンズの環境を扱った曲である。 「ソルト・オブ・ザ・アース」、「ストリート・ファイティング・マン」、「シンパシー・フォー・ザ・デビル」である。 いずれもシゾイド的な曖昧さが歌詞の特徴である。 ストーンズは、自分たちの周囲で起こっている若者のエネルギーの爆発を認識している。 これらの闘争に内在する暴力を認識している。 そして、それを根本的な変革のための運動としてとらえ、深く共感している。 しかし、彼らはあまりにも皮肉屋で、自分たちが本当に行くことはできない。
歌詞の中には、道徳的・政治的激変の象徴があふれている。「悪魔への共感」では、「富と味覚の男」ルシファーが晩餐会で客の間を行き来するが、ケネディ家の二人を殺す。「野良猫ブルース」では未成年の娘が家出してレイプされるが、「死刑ではない」と正当化し、路上で行進し、罪人は聖人、警察は犯罪者である。 同時に、ストーンズの声はどこか別のところにある。「No Expectations」の叙情的、音楽的印象主義や「Moonlight Mile」のペンタトニックなオリエンタリズムは反応、記憶、夢であって行動ではない。「Street Fighting Man」は実は闘いにコミットしていないし、放蕩息子は遺産を持っていても自分ではやっていけないのである。 口先ばかりで、行動が伴わない。 プロレタリアへのオマージュである “Factory Girl “と “Salt of the Earth “は、明確なテーマを提示する唯一の曲である。 つまり、『ベガーズ』に始まり『エグザイル』に終わるアルバムは、しばしば矛盾をはらんだとしても、ストーンズの最も認知度が高く耐久性のあるイメージを確立した、本物の音楽像を描いているのである。 ファンにとって、それ以降のバンドのすべての段階は、この基本的なマスター・シナリオのバリエーションなのである。 それは、キース・リチャーズによって大きく形作られた、ブルースの移住的側面に由来する、追放された旅人としての感覚と、あらゆる種類の音楽のルーツに対する大胆不敵で深遠な探求、リチャーズによる、革命的だがあからさまな政治や立場のないタフで不屈の姿勢のようなものである、と言えるかもしれない。 10 アフリカ系アメリカ人や田舎のイディオムへの敬愛に基づく根深い転向、そして重要なのは、追放された人々、黒人、周縁の文化への執着、「低い生活や階段下の生活の幻想」を露わにすることだ。 Exile on Main Street』の頃には、ビル・ワイマン以外はまだ30歳にもなっていなかったストーンズは、旅、喪失、希望、欲望、判断などを語る深いレパートリーを口頭や録音で持ち、亡命時代の豊かなボキャブラリーを構成する、旅慣れたブルースマンになった。 1969年には、1968年のブライアン・ジョーンズの死とそれに続くミック・テイラーの加入により、最初の大きな人事異動があり、音楽的にグループがかつてないほど強くなった時期の到来となった。 ジョン・メイオール・バンドの長いブルースの回廊で音楽教育を受けた若く腕利きのギタリストであるテイラーは、ボトルネックの名手であり、ストーンズに初の真の「リード」ギタリストを提供し、特にライブでは輝かしいソロのセクション、独特の音色、即興を通して彼らの曲調を拡大する結果となった。 1969年はまた、2年半に及ぶ活動休止の後、ツアーへの重要な復帰を果たした。この休止の主な理由は、よく知られた「レッドランズ・スキャンダル」をはじめとするさまざまな薬物逮捕との戦いや、増大する財政難だった12。経済・法的迫害の問題が重なり、1971年に彼らは真の納税者として南フランスへ移住することになったのだ。 しかし、この数年間は、アルバムのリリースを目前にして曲を録音するというシステムを放棄し、より長い妊娠期間と修正を優先させた、新しい曲作りのプロセスも明らかにしている。 ベガーズ』から『エグザイル』までのアルバムに収録されている曲の多くは、実は同時に構想され、最終的なリリースの何年も前に作曲が開始されている-『ベガーズ』以前にはない時系列である。 1969年と1971年にそれぞれリリースされた「You Can’t Always Get What You Want」と「Sister Morphine」の最も古いテイクは、すでに1968年の5月と11月に見つけることができる。 スティッキー・フィンガーズ』(1971年)や『エグザイル・オン・メイン・ストリート』(1972年)に収録されることになる多くの曲は、”Brown Sugar” “You Gotta Move” “Wild Horses” “Dead Flowers” “Loving Cup” “All Down the Line” などすでに1969年に起源を有している。 同様に、”Stop Breaking Down”, “Sweet Virginia”, “Hip Shake “の起源は、バンドがフランスに移住する前、リリースから2年前の1970年に発見されている。 この年表は、ローリング・ストーンズの歴史における独特でまとまった創造的段階を形成している4枚のアルバム間の音楽的な類似性と共通のセッションを証言しています
。